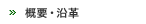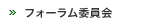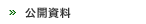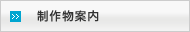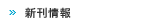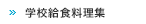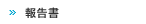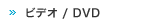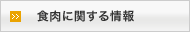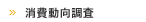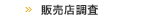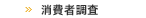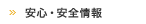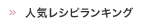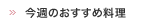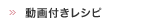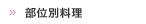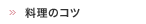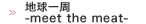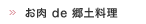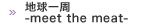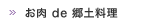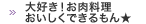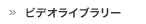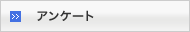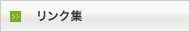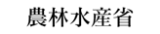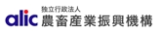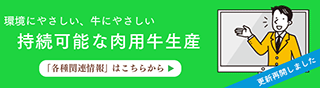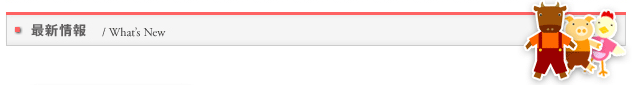| 令和6年度供給リスク増大下の食肉事情等理解醸成事事業【消費者意識調査報告書】 |
| [2025-03-25] | |
| 世界的な食料需要の増大、ウクライナ情勢等によって食料の供給リスクが増大している中、我が国畜産業は飼料価格の高騰等により経営的に厳しい状況に置かれています。こうした中、我が国の畜産業の現状を一般消費者に認識していただくとともに、食肉の合理的な価格形成についての理解を醸成することを目的として「供給リスク増大下の食肉事情等理解醸成事業」を実施しましたが、同事業の一環として行った「消費者意識調査(WEB調査)」と「食肉家計消費等動向分析」の結果を以下の2種類の報告書に取りまとめています。 ①消費者意識調査報告書 一般消費者を対象として、食肉価格の上昇が常態化しつつある中での食肉購入行動の変化、価格上昇許容度、畜産業の現状や食料・食肉の供給リスクについての認識度、生産コスト上昇分の価格転嫁に対する意識等を把握 ②食肉家計消費等動向分析報告書 家計調査を主な分析対象としつつ食品スーパーのID-POSデータ等も活用して、食肉価格の上昇とその常態化による消費者の食肉購買の変化をコロナ禍以前の2019年からの中期的な食肉消費動向の中で把握 調査結果のポイント【消費者意識調査報告書】 (1)食料・食肉価格の上昇と購入行動の変化 ●1年前と比べ最も値上がりを感じている食品は「コメ」(58%)(前年は「鶏卵」)。以下「野菜」(42%)、「パン」(24%)と続くが、購入を減らした食品は「特になし」が45%と最多。食肉の中では、牛肉の購入を控える動きが前年以上に顕著。 ●食肉の中で最も購入量が多いのは豚肉で、次いで鶏肉、牛肉、ひき肉の順。また、牛肉と豚肉の選択率は前年より減少した一方、鶏肉は増加。豚肉は60代を 筆頭に全ての年代で最も選択率が高いが、鶏肉は若年層ほど選択率が高く、牛肉は40~50代の子育て世代の選択率が低い。 ●牛肉の中で最も購入量が多いのは「和牛以外の国産牛肉」(29%)で、次いで「輸入牛肉」(27%)(前年は「輸入牛肉」(34%)が最多)。「和牛」の購入量は高齢層が多く、若年層では少ない傾向。 「牛肉を購入しない」との回答は12%。牛肉を購入しない理由としては、「価格が高いから(コストパフォーマンスが悪いから)」が69%と最も多く、以下「豚肉や鶏肉の方が好きだから」(37%)、「牛肉が好きでないから(美味しいと思わないから)」(17%)と続き、「環境に悪影響を与えるから(牛のゲップ等)」は2%と少なかった。 (2)食肉の購入行動と理由 ●食肉購入の際には、約7割の消費者が「価格」を最も重視しており、高齢層では「鮮度」「産地・ブランド」も考慮する傾向。また、「霜降りの度合い・脂身の割合」は牛肉で20%と特徴的に高い選択率。さらに値上がりが進んだ場合には、価格の優先度は上がる一方、それ以外の要素は優先度が低下。 ●国産食肉か輸入食肉かの選択要因としては、約7割が「価格」と回答しており、 前年よりも「価格」や「国産か輸入か」を意識する傾向。また、消費者の約半数 が、いずれの食肉についても価格差が10%までならば国産食肉を選択すると回答 したが、その選択率は前年よりやや減少。 ●食肉価格の値上がりを許容できない人は前年よりやや増加していたが、許容できる人にあっては値上がりの許容度が前年よりも上昇。また、「値上げは許容できない」は国産食肉が約10ポイント低く、「10%まで許容できる」は約5ポイント高い等国産食肉の方が輸入食肉よりも許容度が高い。また、高齢層ほど許容度が高く、国産食肉と輸入食肉との差も大きくなる傾向。 (3)供給リスクへの消費者意識 ●畜産業の現状(生産費に占める飼料費の割合、飼料の輸入割合、近年の飼料価格の高騰、肉用牛農家の減少)についての認知には年代間の格差が見られ、高齢層ほどそれらの認知度が高く、現状を心配する傾向が強いものの、過半数が畜産業の現状を知らない状況であった。 また、消費者の約7~8割が畜産業の現状を心配するものの、畜産業の生産構造(「家畜を育てる以上、飼料にコストがかかるのは当然」、「農家全体が減少」等)や経営環境(「国産より輸入飼料の方が安価」、「円安」等)等を理由に、約2~3割の消費者は畜産業の現状を容認。 ●生産コストの上昇分を食肉価格(小売価格)に転嫁することについて、消費者の50%が生産コストに応じた価格上昇を容認しているが、その割合は前年(52%)よりやや減少。また、消費者の約半数(55%)は既に価格転嫁は行われていると認識しており、現状とはギャップが見られた。畜産業の現状について理解がある高齢層でも同認識は強く、前年よりも増加。 ●今後の食料や食肉の供給については8割以上の消費者が不安を感じていた。その理由としては「価格上昇」が57%と最多だが、前年(62%)より減少し、「安全性」(49%)や「食料自給率」(45%)などの選択率が前年より上昇。 ●食肉価格の値上がりの許容度について、畜産業の現状や食料供給リスクについての情報を提供した後に再度尋ねたところ、2回目は「値上げは許容できない」は9ポイント減少し、「10%まで(15%まで、20%まで、20%を超えても)許容できる」の選択率が増加する等、価格許容度は情報提供前の1回目より上昇。「値上げは許容できない」は全ての年代で減少し、特に30~60代の女性で大きく減少。 ●食肉の安定供給のために日本の畜産業にとって必要なこととしては、「飼料の自給率の向上」(64%)、「飼料の多様化」(45%)、「飼料の安定的輸入」(34%)と飼料関係が上位を占めた。また、消費者が取り組むべきこととしては、「食品ロスの削減」(75%)、「地産地消」(55%)が多く、高齢層ほど選択率が高かった。 |


|