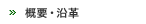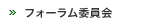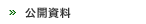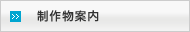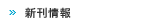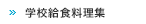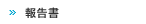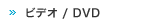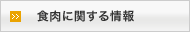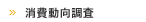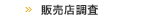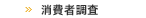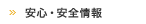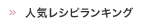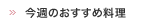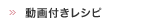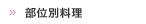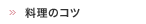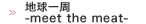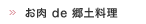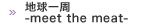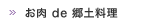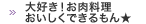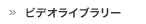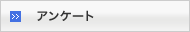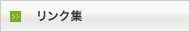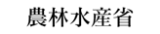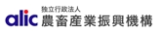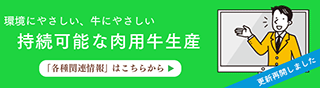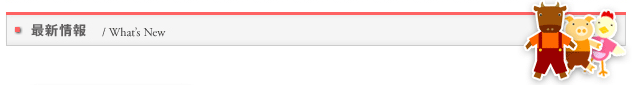| �ߘa�U�N�x�������X�N���剺�̐H����������������Ɓy�H���ƌv����������͕��z |
| [2025-03-25] | |
| �@���E�I�ȐH�����v�̑���A�E�N���C�i����ɂ���ĐH���̋������X�N�����債�Ă��钆�A�䂪���{�Y�Ƃ͎������i�̍������ɂ��o�c�I�Ɍ������ɒu����Ă��܂��B�����������A�䂪���̒{�Y�Ƃ̌������ʏ���҂ɔF�����Ă��������ƂƂ��ɁA�H���̓K���ȉ��i�`���ɂ��Ă̗������������邱�Ƃ�ړI�Ƃ��āu�������X�N���剺�̐H����������������Ɓv�����{���܂������A�����Ƃ̈�Ƃ��čs�����u����҈ӎ������iWEB�����j�v�Ɓu�H���ƌv����������́v�̌��ʂ��ȉ���2��ނ̕��Ɏ��܂Ƃ߂Ă��܂��B �@�@����҈ӎ������� �@�@�@��ʏ���҂�ΏۂƂ��āA�H�����i�̏㏸����ԉ������钆�ł̐H���w���s���̕ω��A���i�㏸���e�x�A�{�Y�Ƃ̌����H���E�H���̋������X�N�ɂ��Ă̔F���x�A���Y�R�X�g�㏸���̉��i�]�łɑ���ӎ�����c�� �@�A�H���ƌv����������͕� �@�@�@�ƌv��������ȕ��͑ΏۂƂ��H�i�X�[�p�[��ID-POS�f�[�^�������p���āA�H�����i�̏㏸�Ƃ��̏�ԉ��ɂ�����҂̐H���w���̕ω����R���i�ЈȑO��2019�N����̒����I�ȐH��������̒��Ŕc�� �������ʂ̃|�C���g�y�H���ƌv����������͕��z �i�P�j�ƌv�x�o�̓��� �@����30�N�ԉ����Ő��ڂ��Ă���������2022�N����傫���㏸���A����ɔ����ƌv�ł̏���x�o�������B����x�o�̂����ő�̊����i����1�N��29.9%�j���߂�H�����2019�N��ł͑������Ă�����̂́A���̊Ԃ̏���ҕ����w���iCPI�j�̐L�т�������Ă���A�ߖ�u��������������B �@�@�@�Ȃ��A�����������̔N��ȏ�̐L�ї��ƂȂ��Ă���20��͏���ӗ~�������ŁA�H������͂��ߗl�X�Ȕ�ڂŎx�o���z�������B �@�����H�E���H�E�O�H�ʂł́A���H�ւ̎x�o�̓R���i�Ђł̑���������v�ɂ�葝�������㌸���X���Ő��ڂ��Ă������A�����㏸�̉e���ɂ��2022�N�㔼�ȍ~�͑����X���Ő��ځB����A�R���i�Ђő啝�Ɍ��������O�H���R���i�БO��2019�N�����鐅���܂ʼnB�����������A���H��2019�N�ȍ~��т��đ����B �@�@�@�N��ʂł́A20�オ���H�E�O�H�Ƃ��Ɏx�o��傫���L���B�n��ʂł́A�k�C���Ⓦ�C�A�l���ŊO�H�ւ̎x�o�͌���/�����ł������A���H�ւ̎x�o���������Ă���A�����n��ł̊O�H������H�ւ̎��v�V�t�g�������B �@�����H�x�o�ł́A���ވȊO�͍w���p�x��2019�N��ł�������������Ă��钆�ŁA���ނ͔�r�I�w���p�x�̌��������Ȃ��A�����Ƃ����������̂͋���ށB �N��ʂł́A20��͓��ނ��͂��ߑ����̐H�ނւ̓��H�x�o�����̔N��ȏ�ɑ傫�������B�n��ʂł́A�k�C���ł͓��ނƓ����ށA�l���ł͋���ނւ̎x�o���������铙�A�n�悲�ƂɈقȂ����X��������ꂽ�B �i�Q�j�H���̏���� �@�����N���Ɖ��H���̎x�o���z�̔䗦��8�F2�i����1�N�ԁj�B�R���i�Ђ̑���������v�ňꎞ�I�ɑ������A���̌㌸���X���ł��������N���̎x�o���z�́A�ŋ߂̓R���i�Ђ̎����ɕC�G���鐅���ɉB�������A2023�N��������͎x�o���z�̐L�т�CPI�̐L�т�������Ă���A�ߖ�X����������B ���N���ւ̎x�o���z�i����1�N�ԁj��40�`50�オ�ő���20�オ�ŏ��ł�����̂́A2019�N��ł�20�オ���̔N��ȏ�ɑ����B�x�o���z�͐����{�ő����X���ł���A�����������A�k�C���̎x�o���z�͑S�����ς�菭�Ȃ����̂́A2019�N��ł͑��̒n����ˏo���đ����B �@�������͐��N���x�o���z��26.5���i����1�N�ԁj���߂Ă���B�x�o���z��2021�N��������̉��i�㏸�̉e����2019�N���݂��ێ����Ă�����̂́A�w�����ʂ�w���p�x�͌����B���ɗA��������CPI�́A2021�N�㔼���獑�Y�����ȏ�ɑ傫���㏸���Ă���A�H�i�X�[�p�[�ł͍��Y�����ȏ�ɗA�������̔�����z�������B �܂��A����w�قǎx�o���z��w���p�x�������A���ω��i�i100���P���j������w�قǍ�����20���70��Ƃł͖�2�{�̍��B2019�N��ł́A�قƂ�ǂ̔N��ōw�����ʂ��������钆�A20��͑������Ă���A20��̋�������̍D��������������B�x�o���z�͐����{�������A�ł������ߋE�ƍł����Ȃ��k�C���ł�3�{�ȏ�̍������邪�A2019�N��ő��������͖̂k�C���A�k���A���C�B �@���ؓ��͐��N���x�o���z��42.0���i����1�N�ԁj���߂Ă���B���N���̒��ōł��x�o���z�������A�w�����ʂƍw���p�x�͊ɂ₩�Ɍ������Ă��邪�A�ˑR�Ƃ��Ēꌘ�����v���ێ��B�����A�A���ؓ��̉��i��2022�N���߂���㏸�������Ă���A�H�i�X�[�p�[�̗A���ؓ��̔�����z��2023�N��������2019�N��������Đ��ځB �@�@�@�܂��A40�`50��̎x�o���z�ƍw�����ʂ������A2019�N��̐L�т��傫���B����50��̍w�����ʂ̑����������B���ω��i�i100���P���j�͍���w�قǍ������̂́A20���70��̍���1.3�{�Ƌ����قǑ傫���Ȃ��B�����{�ł̎��v�������A2019�N��ł̎x�o���z���k�C�����͂��߂Ƃ��铌���{�������{�ȏ�ɑ����B�����������A��B�͎x�o���z�A�w���p�x�Ƃ��Ɍ����ɐL���B �@���{���͐��N���x�o���z��23.6���i����1�N�ԁj���߂Ă���B2019�N�ȍ~�A�x�o���z�����łȂ��A�w�����ʁA�w���p�x�������B2022�N�㔼����CPI���傫���㏸���Ă��邪�A�x�o���z��CPI�������Đ��ڂ��Ă���A���i�̏㏸�͂��������̂́A����͌����B �@�@�@�܂��A40�`50��̎x�o���z�ƍw���p�x�������A2019�N�Ɣ�ׂĂ����̐���ȏ�ɑ����B�N��ɂ�镽�ω��i�i100g�P���j�̍���1.1�{�Ə��������̂́A2019�N��ł̑������̔N��ɂ�鍷�͑��̐H���ȏ�ɑ傫���B��B���͂��߂Ƃ��鐼���{�ł̎x�o���z���傫�����A2019�N��ł͖k�C���Ɖ���̐L�т������B �@�������E�ؓ��E�{���E�����т����ɂ��Ĕ�r����ƁA�����͉��i�㏸�̉e���Ŏx�o���z����2019�N��Ńv���X���ێ����Ă��邪�A�w�����ʂ͌������Ă���A�����T���̌X���B�x�o���z�͑����X���̓ؓ����w�����ʂ�2021�N�ȍ~�ɂ₩�Ȍ����X���B�{���ƍ����т����͎x�o���z�E�w�����ʂƂ��ɂ���1�N�قǑ傫�������B �@�@�@2019�N��ł́A������20��A�ؓ��E�{����40�`50��̎x�o���z�������B �@�@�@�����͋ߋE�A�ؓ��͓����{�A�{���͋�B�Ƃ����n��I�ȍ��ق͈ˑR�Ƃ��Č����邪�A2019�N��ł́A���ނ̏���ォ�����k�C���Ŏx�o���z���������A��B �œؓ��̎x�o���z���������铙�n�悲�Ƃ̐H������ɕω��������Ă���B |


|